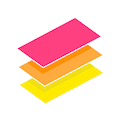『自分は相手に何を期待しているか』を自覚することから、マネジメントは始まる
評価フィードバックのために期待役割を翻訳する。チームメンバー同士で期待値をすり合わせる。
エンジニアリングマネージャーとして仕事していると、こういった期待値の調整をする場面はよくありますよね。
組織やチームの一員として活動しているエンジニアにとって「期待値」は意識せざるを得ないものですが、今回は期待される側ではなく期待する側に注目して、「何を期待しているか」「どのように期待を伝えているか」を整理してみようと思います。私がチームマネジメントやスクラムマスターをしていてよく陥る失敗を思い返しながら、自分への注意喚起を兼ねて整理してみます。
自分の中の期待を分類する
私は期待の種類を4つのレイヤに分類して捉えています。

イメージしやすい順に、下から見ていきましょう。
行動意識への期待
ひとつの出来事・仕事・タスクを実行する過程で、どのような姿勢・意識で臨んでほしいかを指します。「自主性を持って取り組んでほしい」といったものです。
タスクの成否以前に、まずはどういう心構えで取り組んでほしいかを期待している段階です。しかし現実世界では、「もっと真面目にやれ」といった『意識への期待』を言いつつも、タスクを完遂することを暗に期待しているケースがあったりします。
「自分が相手に何を期待しているか」を正しく理解していないことで何かしら問題が起きそうな匂いがすでにし始めていますね。
手段への期待
ひとつの出来事・仕事・タスクについてどのような方法・プロセスで取り組んでほしいかを指します。「毎日決まった時間に進捗を報告してほしい」といったものです。
これは行動意識への期待よりは実践的で具体的です。しかしまだタスクの成否よりも前段階です。「成功するか否かは置いておいて(自分が責任を持つので)、まずは言われた通りの方法で手を動かしてほしい」という期待が『手段への期待』です。
(法令遵守の観点などで厳密に手順を指示する場面もありますが、これは期待ではなく指示なので今回の話題からは除きます)
結果への期待
ひとつの出来事・仕事・タスクについてどのような結果を出してほしいかを指します。「スケジュールに間に合わせてほしい(間に合わせてくれれば手段はお任せする)」といったものです。
裁量のある仕事を依頼するときは、「結果への期待」が込められていることが多いでしょう。
状態への期待
ひとつひとつの出来事・仕事・タスクについてではなく、有機的で連続的な活動を通じてどういう状態を維持してほしいと思っているかを、ここでは「状態への期待」と表現します。「案件の優先順位に沿ってうまく計画立てて進行している状態を維持してほしい(ときには失敗することもあるだろうが、その改善も含めて停滞せず前進し続けていればよい)」といったものです。かなり裁量の高い任せ方ですね。
* * *
この記事内では「状態への期待」「結果への期待」を高レイヤの期待 、「手段への期待」「行動意識への期待」を低レイヤの期待と呼び分けます。
他者に何かしらの期待を抱くとき、まずはこれらの便宜的な分類に照らし合わせて期待の内容を自覚することが、マネジメントのスタート地点です。
中には明確に線引できない期待もありますが、それを自覚することがこの便宜的な分類の役割です。
「本当の期待」を見誤っていた事例
具体例を挙げて考えてみます。
例えばアルバイトや学校行事などで「もっと真面目に取り組んでほしい」なんて思ったことは誰しも1度くらいはあるのではないでしょうか。また上司などから「進捗を報告してほしい」と言われたことのある人も多いと思います。これらのセリフを言った人の胸のうちには、期待が隠れています。
仕事上では「仕事を依頼する」場面で、胸の内では何かしらの期待を抱いていることが多いですが、私は根源にある本音を見抜けていないことがよくありました。
たとえば、
- 「もっと真面目に取り組んでほしい(行動意識への期待)」は、「ミスを減らしてほしい、減らすための改善を継続してほしい(状態への期待)」という本音が隠れている
- 「進捗を報告してほしい(手段への期待)」は、「遅れずに結果を出してほしい(結果への期待)」という本音が隠れている
こういった本音に気づけていませんでした。
つまり低レイヤの期待の裏に、高レイヤの期待が隠れていたわけです。
高レイヤの期待とは、「(あなたなら手段や態度は指示せずとも大丈夫だろうから)結果を期待する」や「(あなたの成果について一定の信頼があるから)状態を期待する」といった具合に、信頼を土台にして成り立ちます。自信を持って相手を信じることができないと高レイヤの期待を抱けないか、もしくは抱いているのに言葉にして伝えられません。
特に仕事を依頼する・依頼されるという関係性には上下関係や優劣関係が含まれていることが多いです。それでも相手を信頼して期待を抱けるかどうか、これが期待値マネジメントの質を左右させるのではないでしょうか。
ここまで自覚できれば、あとは期待の本音をそのまま言葉にするだけです。
* * *
頭で理解したからといってすぐに行動できるわけではないのが、人間の難しいところで面白いところですね。
この記事を書きながら、今日も私は目的の期待と手段の期待が混同する業務依頼をしてしまいました。それでも、その過ちを振り返り「次はこうやって伝えよう」と試行錯誤していくことで、きっといつかはより自然に上手く期待値を伝えられるようになるはずです。
チームメンバーに仕事を任せ、彼らの能力の1歩先の期待値を設定することが、マネージャーとしてできる最初の仕事であるはずだと信じて、まずは自分自身の「期待心の奥にある本音」に向き合い続けようと思います。
数年後の自分がこの記事を読んで「当時はこんなことで悩んでいたのか、今では当たり前にできるよ」と言ってくれると信じて、今回はここまで。
追記 - 5年後の自分から、あの頃の自分へ
5年後の自分が追記します。
まさに読み返して「当時はこんなことで悩んでいたのかあ」としみじみしました。
マネージャーになりたてだった当時の自分に向けて、Tipsと失敗パターンを2つ書き残しておきます。
「結果の期待」をしているが手段も少し伝えたいとき
仕事を依頼する相手が十分なスキル・経験を持っていて信頼している場合、「結果の期待」をする場面が多いでしょう。ただ、相手にとってまったく新しい仕事である場合は、結果を期待しつつも手段について補足したくなることもあります。そのときは手段を提案するという手があります。
「基本的に手段はおまかせするけど、悩んだときは〇〇をしたり、Aさんに相談したりしてみても良いと思います」
といった具合に、手段を提案しつつ取捨選択は相手に委ねると、期待値を維持したまま手段を伝えられます。
期待しすぎてしまったとき
チームメンバーにある仕事をまるっと渡して「期限までに完了する」という「結果の期待」したものの、どう進めていいか悩み行き詰まってしまっていたことがありました。それをみて、上述のように手段を提案して少しずつ前に進めてもらったのですが、今振り返ると、これは過剰な期待だった可能性があります。
いきなり完遂を目指すのではなく「まずは設計についてチーム間で合意を得るところまでやってほしい」といった具合に結果を分割したり、「まずは設計について自身でたたき台を作って、それをもってメンバーに相談してほしい」と最初から手段の期待で臨んだりしても良かったのかもしれません。
相手の力量や想定を大きく超えた期待をかけてしまうと丸投げになってしまいますし、その逆で不用意に細かく(または低レイヤに)期待しすぎるとマイクロマネジメントになってしまいます。
このバランス感が、期待値マネジメントの肝なのかもしれませんね。
* * *
当時の自分はEMとして考えるべきことの多さに頭をパンクさせながら、目の前の課題に1つ1つ向き合っていたことを思い出しました。
最近の私は、チームのマネジメントを新任EMにバトンタッチすることが度々あり、託された彼らも同じように多くの悩みにぶつかりながら前進しているのだと思います(エンジニアとして優秀で、マネジメントへの関心も意欲も高い彼らなので、心配は無用ですが)。
そんな頼れる新任EMたちに、当時の自分と5年後の自分の知見が少しでも役立てば嬉しい限りです。