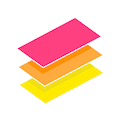1on1再入門 - “傾聴する”から”好奇心を持って問いを設計する”へ
「1on1では聞く側に徹しましょう」「8割以上の時間を部下の話に耳を傾けるべき」
こういったアドバイスに私も従っていた時期がありました。
当時の私は相手の話にじっと耳を傾け、「うんうん」と相づちを打ち、「それで?」と続きを促す。散々相手に話してもらったものの、1on1の後にどこかすっきりしない気持ちが残る。そんな1on1をやっていました。
「これは本当に意味のある時間だったのか?」
「ただ話させて終わってしまったのではないか?」
こういったモヤモヤの原因は、話を聞くことに集中しすぎて相手の変化や考えを深めるような「問い」をまったく投げられていなかったことにあったと、今なら分かります。そして当時の自分にどうアドバイスすべきかも明確です。
今回はそれを書き起こしてみようと思います。
本題の前に、前提について補足しておきます。
1on1の目的は組織やチームの文化によって異なりますが、この記事では、1on1を単なる報告や進捗確認の場としてではなく、相手の内面や成長に向き合う「探索の場」として活用することに重点を置いています。
「探索により、変化や思考の深化を目指す時間にしたい」という価値観のもと、当時の私の失敗の理由を明らかにし、改善のためのアプローチを書いていきます。
- 傾聴は「作法」ではない、結果として現れる「状態」
- 探索の場における「問い」をどのように設計するか
- 「問いを設計する自分」を置いてけぼりにした失敗例
- 「純粋に会話を楽しむ自分」と「メタ的に問いを設計する自分」を共存させる
- まとめ
傾聴は「作法」ではない、結果として現れる「状態」
傾聴とは、
相手の話に注意深く、真摯に、共感をもって耳を傾けることで、相手の気持ちや考えを深く理解しようとすること
だと言われています。
ですが「よし、じゃあ今日から傾聴するぞ」と自動詞的に実践するものではなく、「相手に敬意を持ち、純粋な好奇心のもと、相手との対話を楽しむ」その結果として現れる姿勢が「傾聴」だと私は考えています。
言い換えると
- 「1on1の時間になったから話を聞こう」という惰性的スタンス(敬意がない)
- 「マネージャーとして話を聞かなきゃいけない」というやらされ感(好奇心がない)
- 「淡泊に『それで?』と相槌を打つ」などの会話を楽しむ気持ちの欠如
といった状態では、どんなに聞く時間を長く取ったところで傾聴にはならないですし、1on1も機能しないということです。
加えて、1on1における傾聴をうまく実践するための糸口が「問い」です。
「聞く」ためには「話してもらう」必要があり、話してもらうには「問いかける」必要があります。この問いかけの質が、1on1で相手の話を聞く質に直結するわけです。
問いかけの質など全く考えてもいなかった当時の自分にも伝わる表現を意識して、問いの設計方法を深堀りしてみます。
探索の場における「問い」をどのように設計するか
1on1を探索の場にするという前提に立つと、「相手が自身のことをより深く理解する」「考えを一歩深める」ような対話が重要になります。そのためには、相手の思考の『地図』を広げるような問いが役に立ちます。
そのためには、以下の3つのいずれかの問いを目指すと良いです。
1. 過去の出来事の意味付けを促す問い
人は経験そのものではなく、「その出来事をどう捉えたか」によって行動や感情が変わります。
たとえば「そのとき、どんな意味があると感じた?」という問いは相手の内面で起きていた認知や解釈を引き出し、単なる出来事の報告から一歩踏み込み、体験に意味付けし言語化する対話を生み出します。
2. 暗黙的な価値観や前提を言語化させる問い
人の行動や判断には、無意識のうちに持っている価値観や前提が強く影響します。
たとえば「それって、どういう状態が理想だと感じてた?」のような問いは本人がふだん意識していない「自分にとって大切なこと」をあぶり出し、自己理解を深めるきっかけになります。
3. 行動の背景にあるモチベーションや感情を掘り下げる問い
表面的な行動だけを聞いても、その人の芯にある行動指針や動機には迫れません。
「それを選んだとき、どんな感情があった?」のような問いによって行動の背後にある感情にアクセスすることで、より本人にとって意味のある内省が促されます。
これら3つの問いは、目に見える「表面的な体験」から、目に見えにくい「内面の揺れ動き」を探索する橋渡しをしてくれます。この内面へのアクセスを1on1の場で実践することで、変化や成長のきっかけになったり、内省の習慣づくりになったり、経験を構造的に捉える訓練になったりするわけです。
「問いを設計する自分」を置いてけぼりにした失敗例
ここまでの話で、当時の自分が良い1on1をするには適切な問いの設計をする必要があったと分かりました。3つの問いの設計方針もある程度言語化できています。
課題と解決策が揃っているので今はさぞ良い1on1ができているのだろうと思いたいですが……正直なところ今でもまだまだ失敗することがあります。その例を紹介します。
たとえばある1on1で「あろえさんがやった〇〇の取り組みのおかげでチームが助かっています」といった嬉しいフィードバックをもらったとき、ついその言葉に舞い上がり、「ありがとう!そう思ってくれていたんだね」と会話を弾ませてしまうことがあります。
しかし終わったあとに冷静にその時間を振り返ると、「その〇〇を自分でもできると思う?」「役立ったと感じた要素って何だと思う?」といったような相手の内面にダイブしていく問いかけができていれば、相手の思考の『地図』新たな観点が描き加えられるような対話をできたかもしれません。
会話を楽しむ自分が前面に出すぎて、『問いを設計しようとする自分』を置き去りにしてしまう失敗を、今でもちょくちょくやらかしています。
「純粋に会話を楽しむ自分」と「メタ的に問いを設計する自分」を共存させる
この失敗談は、「会話を楽しみすぎて問いを設計する観点が抜け落ちた」例でした。
もちろんその逆の失敗もあります。問いの設計に意識が向きすぎた結果、会話を俯瞰しすぎて当事者感が薄れ、相手との距離が遠のく感覚に陥る失敗です。
そうなると相手の感情や表情の変化を見落としてしまったり、また自分のリアクションが薄くなったりと会話を楽しめていないような反応が出てしまったりします。
これらの例からわかるように、1on1をしているときは「純粋に相手との会話を楽しむ自分」と「会話の流れをメタ的に捉え問いを設計する自分」の間を行ったり来たりしています。
1on1がうまくいっているときは対話の中で頻度高く行き来できますが、振り返って失敗したなと感じるときはどちらかの自分に傾倒していたり、行き来の回数が少なかったりします。
2つの自分をどのようなバランスで両立するかは、人や状況にとっても異なると思います。ですので「うまくバランスを取ろう」と思うより、1on1がうまくいかなかったときにバランスを振り返る、という捉え方が良いでしょう。目指すべき指針ではなく、ふりかえりの基準ということです。
そして「2つの自分の往復」という観点では、今の私もまだまだ練習中です。
ですが、この段階に到達できたのは、問いの設計に慣れてきたからだと言えます。2つの自分の往復に意識を向ける余裕が生まれたなと思ったら、それは問いかけの経験値が十分に溜まった合図なのかもしれませんね。
まとめ
私が1on1でやらかした多くの失敗を思い出しながら、当時の1on1を着実に前進させるためのアドバイスを書き表しました。
- 1on1は探索(対話)を通じて、相手の変化や思考の深化を促すもの
- 傾聴は「する」ものではなく、好奇心を持って会話を楽しむ結果として「現れる」もの
- 「聞く」には、「話してもらう」。「話してもらう」には「問いかける」
- 問いを設計する3つのガイド
- 過去の出来事の意味付けを促す問い
- 暗黙的な価値観や前提を言語化させる問い
- 行動の背景にあるモチベーションや感情を掘り下げる問い
- 「会話を楽しむ自分」と「会話をメタ的に観察し問いを設計する自分」の行き来がうまくできたか、という基準で1on1をふりかえってみる
といった内容でした。
最後に少し抽象的な話をすると、今の私にとって「問い」は単なるテクニックではなく「自分のあり方」なのだと思います。
人とどのように関係をつくっていきたいか、人のどのような感情に興味を持つか、相手の変化や成長に伴奏したいという根源的な願いをどう実現させるか、信頼をどう得るか、といったことを問いを通じて体現しているのだと思います。
ですので、たとえ意識的に問いを設計しなくとも、私がする問いかけには私を構成する要素が色濃く出ているでしょうし、それにより相手が私を信頼し、私と良い関係を築いてくれたらとても幸せな気持ちになります。
「マネージャーになったから1on1をしなきゃ」「ちゃんと傾聴しなきゃ」
なんて思っていた自分がここまで問いと向き合えるようになったことは、マネージャーとして一回り成長した証なのかもしれません。
よければ、皆さんも「問い」に向き合ってみてください。