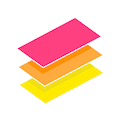議論を“立て直す”ときに使える、力点と作用点を効かせるファシリテーション
会議のファシリテーションをしていて、「論点がかみ合わない」「発言は出ているのにまとまらない」と感じることはないでしょうか。そんな場面では「どの論点に力を入れれば、どの結論に影響を与えられるのか」がブレてしまっていることがあります。
これを議論の『力点』と『作用点』が入り乱れてしまい迷走しているという視点で捉えると、ファシリテーションの糸口が見えてきます。
テコの三要素と議論の対応関係
「テコ」は以下の3つの要素で構成されます。
- 力点:議論で注力すべきテーマや問い
- 作用点:議論の結論により影響を与える箇所。現場の困りごとやリターンのある領域
- 支点:動かない前提、制約、背景
「今どこに力を加えようとしているのか(=力点)」「何を動かしたいのか(=作用点)」というテコの原理に似た構造が、議論の中には隠れています。 議論が迷走するときはこれらにズレがあり、一直線に繋がっていない可能性があります。ファシリテーターはそれを見極め整理することで、議論を立て直すことができます。
今回は3つのファシリテーションTipsを紹介します。
1.まずは「作用点(何に影響を与えたいか)」を見極める
「朝会をもう少し短くできないか?」という議論が出たときのことです。
一見すると議論のテーマは明確ですが、よく聞くとそれぞれの発言者が持っている目的が違うことがあります。
- Aさん「会議で作業を中断させたくない」
- Bさん「冗長な報告が多く、時間を無駄にしたくない」
- Cさん「必要な情報共有が抜けてしまうのが心配」
このように、同じテーマの下に異なる作用点が混在していると、議論はかみ合いません。
こういう場面でのファシリテーションは、まずは各々がイメージする作用点──つまり「何を良くしたくて議論に参加しているのか」を明らかにすることを目指します。参加者一人一人の背景や意図を明らかにすることが議論の準備として必要なわけです。
2.作用点がバラバラなときは、共通する力点(議論の焦点)を見極める
作用点が散っていて収集がつかないときは「どこに議論の焦点を置けば、複数の作用点に影響を与えられるか」を探るようファシリテーションするのが1つの手です。
前述の朝会の例では、目的が「集中力を維持したい」「作業時間を無駄にしたくない」「情報共有を保ちたい」に分かれていました。
作用点がバラバラなので、それらに共通する議論の焦点──つまり「何を変えれば全ての目的を満たせるか」を、力点にして議論を進めてみます。それでも解決策が見つからない場合は、「作用点の中で譲れる(譲れない)要素は何か」に論点を移し、のちに「全ての作用点にほどほどに効く」現実的な解決策を探す議論になっていくかもしれません。
このようにファシリテーターは「議論の焦点をその場その場で見極め、段階的に変える」アプローチをとることで議論を前進させていきます。
3.作用点と力点が入り混じっているときは、一時的に力点を絞り込む
ふりかえりなどのオープンな議論では、参加者ごとに異なる課題意識(作用点)が出され、話の焦点が定まらなくなることがあります。
たとえば、かつてふりかえりで「開発体験をもっと良くしたい」というテーマで話し合っていたら、以下のような作用点が並びました。
- レビューの質を上げたい (コード品質)
- リリース作業を楽にしたい (運用効率)
- オンボーディングを整えたい (育成コスト)
こんなときに有効なのが、「まずどこから議論するか」を合意し、議論の力点(焦点)を一時的に絞り込むアプローチです。私が使う手法をいくつか紹介します。
実践しやすい軽量な手法
- 参加者の投票で議論する順番を決める
- 「今期中に改善したいものはどれ?」といった問いで絞り込む
難易度は高いが効果が高い手法
- 「重要度と緊急度」「実行しやすさとインパクト」などのマトリクスで整理する
- トピックをグルーピングしたり矢印で相関関係を整理することで、参加者の関心が高いポイントを探る
上にあるものは簡単に実践できる反面、効果はやや弱めです。下にあるものは実践難易度は高めですが参加者と一体となって(高い納得感や共感をもって)作用点を絞り込める可能性が高いです。
今回の例では「作用点がバラバラ」な例を挙げましたが、実際には「力点と作用点が入り乱れた意見が集まる」ことがほとんどです。
たとえば「〜〜だから、〇〇したい」といった提案は、前半の「〜〜」部分は「狙い・意図」であるため作用点となり、後半の「〇〇」部分は「具体策」なので意見が割れる可能性の高い論点であり力点となり得ます。これの整理も同時にやれると更に絞り込みやすいです。
強調しておくと「作用点」「力点」という言葉はあくまで比喩です。厳密に分類しすぎる必要はありません。
大切なのは、「何に影響を与えるために」「ここで何を議論するのがもっとも効果的か」を整理しながら進めることです。そして、こうした整理をファシリテーターだけが担うのではなく、参加者と一緒に行えるようにする工夫を持っておくとファシリテーションはグッとしやすくなります。
まとめ
議論が迷走や停滞してしまったとき、ファシリテーターにできることの1つは、力点・作用点の構造を見抜きズレを解消することです。そのための3つのTipsを紹介しました。
「制約が何か(支点)」「効果を出したいところはどこか(作用点)」「そのために今考えるべきポイントはどこか(力点)」の見定めは、個人で考えごとをしているときには自然とやっていることかもしれません。それを議論の場に広げ、議論全体を1つの思考活動につなぐことが、ファシリテーターの役割です。
しかし、参加者の立場や背景によって思い描く作用点が異なるという点が、これを難しくします。それらに絶対的な優劣や正解不正解を持ち込んでも意味はありません。
違って当たり前、対立して当たり前の意見の集合から、新しい構造を見出し議論を深化させていくことを、参加者全員でできるように導くことがファシリテーションなのだと思います。
参加者の意見に構造を見出し、参加者全員が共感・理解・加担できる議論へと変化させることができれば、行き詰まっていた議論を立て直すキッカケになるはずです。
テコの原理を議論に当てはめる考え方が、ファシリテーター自身の思考整理の役に立てれば、ひいては参加者との共有可能な思考のフレームになれば幸いです。